弱小チームが全国大会を優勝
偏差値35の生徒が東大に合格
結成15年目でM-1グランプリ制覇
こうした苦労話のタイトルを見ると、興味を惹いてしまいますよね。
日本人という種族は、“弱い立場の人間が苦労して這い上がる話”が大好きです。
甲子園に初出場した公立高校の奮闘する姿に、涙を誘われることもあったでしょう。
就職活動でも「あなたが学生時代に苦労したエピソードは?」と聞いてくる面接官がほとんどです。
一体、なぜ日本人はここまで「苦労話」が好きなのでしょうか?
それは【共感性】の強さによるものだと思っています。
本記事では、日本人特有の苦労話好きを筆者の解釈で紐解いていきたいと思います。
・苦労をしてきた経験がある
・頑張っている人を応援したくなる
・SNSでシェアをすることが好きだ
なぜ日本人は苦労話が好きなのか?
小さい頃から練習を積み重ね、苦労して勝ち取った全国大会で、前回王者を倒す…
誰からも賞賛の声が挙がりそうな苦労エピソードですよね。
一方、ZOZOTOWNの前澤社長が退任した時は、「売り逃げ」「無責任」といった心無い汚い言葉もネットに多く書き込まれていました。
苦労人であるにも関わらず。
日本人は奮闘中の人に対して応援し、成功者に対して嫉妬してしまう事が多いように思います。
紐解いていくキーワードは「共感性」です。
日本人は”仲間意識”や”共感性”の高い種族
突然ですが皆さん。
日本はTwitterの利用率の高さが、世界2位ということをご存じでしょうか?
このたび、私はTwitter Japanの新しい代表取締役に就任しました。世界第二位の市場である日本を成長させるため邁進してまいります。また利用者、広告主およびパートナーの皆さんにとって素晴らしいプラットフォームにするべく事業や業務環境の多様性に取り組むだけでなく健全性にも注力していきます。 https://t.co/OMrQhFaZ2f
— reiko-san (@reikona) November 22, 2021
グルーバル利用者:Global social media research summary 2022(※英語サイト)
Twitterという短文に対して共感や批判を行い、いいね/RT/リプを送り合う…
こうしたサービスの特徴が、仲間意識が強い日本人の特性にマッチしているが故、これだけ多くのユーザーに使われてづけています。
金曜ロードショーで「天空の城ラピュタ」が放送されると、「バルス」が世界トレンド1位になることも定常的になってきました。
当然のようにトレンド世界一 #バルス pic.twitter.com/MK3bFcokss
— sync_sync@C99/31日東1/J-06b (@sync_sync) August 30, 2019
2006年~2010年頃には、国内SNSの先駆けとなった「mixi」も大ブームとなりました。
日記やアルバムに対してコメントや紹介文を送り合い、時には同じ趣味のコミュニティへ参加するというサービスが、日本人の心を鷲掴みしました。
「誰かと繋がっていたい」
「誰かと分かり合いたい」
「誰かと同じ考えでいたい」
なぜこんなにも日本人は、仲間意識や共感意識が強いのでしょうか?
日本という国は、周りが海に囲まれた“島国”です。
民族は基本的には一つで、仲間と共に集団を創り、文化を育み、種族を発展させてきました。 ※琉球やアイヌや移民や細かく分ければ色々とありますが、現在の”日本国”として話します
そうした歴史的な背景からも、仲間意識やチームワークという考え方は、生まれたときから細胞レベルで日本人に備わっています。
それが【共感性】の強さへと繋がっていきます。
苦労は誰もが経験をする

共感性の強い日本人ですが、なぜ苦労話に強く頷いてしまうのでしょうか。
「共感」というコトバを辞書で調べてみます。
「共感」
他人の意見や感情などにそのとおりだと感じること。また、その気持ち。
出典:コトバンク「デジタル大辞泉」
「そのとおりだと感じる」ということはつまり、「自分でも経験したことがある」内容ほど、ヒトは共感するものです。
当たり前のことを言っていますが、これが大切なのです。
なぜなら、“苦労”とは生きる上で誰もが経験をしているからです。
人生を歩んでいくと様々なことがあります。
失敗、成功、苦労、ツラさ、楽しさ、踏ん張る、褒められる、怒られる、幸せ、不幸せ…
成功する前には苦労があります。
失敗の前にも苦労があります。
怒られる前にも苦労があります。
そう、
どんな着地になろうとも、苦労した結果で何かが起きているということです。
そろそろ、”苦労”がゲシュタルト崩壊してきました。
仲間意識が高く共感性の強い日本人は、
「苦労して成功したんだねぇ…」
「苦労したけど報われなかったんだねぇ…」
と、自身の経験と重ね合わせて強く頷いてしまうのです。
憧れよりも嫉妬をしてしまう

先述のとおり日本人は仲間意識が強いため、“異端児”は好まれない傾向にあります。
日本にはスティーブ・ジョブズやマーク・ザッカーバーグのような革命的なビジネスマンが生まれてこないと言われます。
日本人特有の“出る杭は打つ”という特徴も、影響しているのではないでしょうか。
日本がこのIT革命期に惨敗街道を爆進中なのは、日本という社会が異端児の存在を許して来なかったからじゃないかな?たまにホリエモンみたいな人が出てきてもフルボッコするだけだしね。
— Hiroshi Matsui 松井博@Brighture (@Matsuhiro) August 19, 2018
「出る杭を打つ」日本人のメンタリティ。なんとかならないのだろうか。みんな仲良くどんどん貧乏になっていく
— ゆぱ🐾 (@Yupa723) November 15, 2021
非のあることを批判するのは大切なことだけど、それに乗じて色々なことを叩いていく。
我々は杭ではなく人間だ
100人の集団の中で、1人が成功し、99人は普通の生活をしていたとします。
本来は1人の成功者を称えるべきではありますが、心の底から共感できない人が多いのも事実。
99人は普通の生活をしており誰も成功を経験していないため、1人の成功者に対して共感が働きづらくなります。
成功者に対して“憧れ”の感情をいだくよりも、“嫉妬”というマイナスの感情を抱いてしまう事も多いのではないでしょうか。
私は苦労して上手くいっていないのに……
私と同じように、上手くいってない人が仲間だ
そんな気持ちが無意識的に働いている可能性が高いかもしれません。
つまり、成功や失敗といった結果よりも、「苦労」という誰もが通る過程のツラさに対して、日本人は強く共感するのでしょう。
【共感性】なぜ日本人は苦労話が好きなのか?【憧れより嫉妬】|まとめ
・仲間と一緒に歩んでいく事が好きで、共感性が高い
・苦労とは誰もが経験をすること=共感しやすい
・異端児には共感しづらく、嫉妬の対象になりやすい
・結果よりも、「苦労」という過程に共感しやすい
大局の見解をお伝えしたので、もちろんこの限りではないと思います。
しかし、「出る杭は打たれる」風潮を感じている人が多いことも事実。
私が不幸なんだから、あなたも不幸になりなさい。
そんな風潮が蔓延してしまったら、日本経済は停滞どころか後進してしまいます。
誰もが経験する“苦労”という過程だけに共感するのではなく、成功者に対しての共感や憧れが広がる世の中になってほしいと願います。

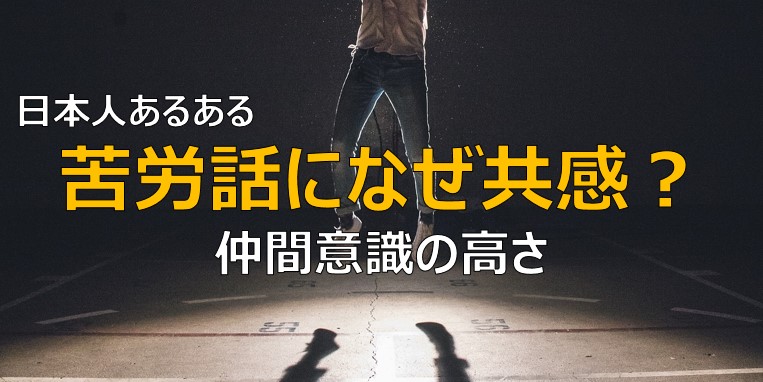

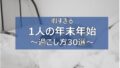
コメント